焼酎で渋抜き!
子どもの頃、甘柿の木は少なく渋柿ばかりでした。
皮をむき、軒先に吊るし、天日にさらした「干し柿」を、祖父は「あまぶし」と呼んでいました。正しくは「あまぼし」であり、有名な「あんぽ柿」は、「あまぼ」が「あんぽ」に転じたものらしいです。
渋柿の皮むきを祖母にばかりやらせていた祖父は、「あまぶし」の出来上がるのが待ちきれなくなったのでしょう。どこからか焼酎で渋抜きする方法を聞きつけ実践していました。
養豚用のビニールの飼料袋(70リットル位)をよく洗い、渋柿を半分ほど詰め、焼酎をふりかけます。そして開口部を麻縄で縛り、冷暗場所に放置するのです。
すると不思議なことに、しばらく経ったある日、渋柿は確かに赤く柔らかい甘柿になっていました。
食感はぶよぶよで好みのわかれるところですが、子どもの頃の僕はその柿で数少ない甘味を堪能していたのでたいへん美味しかった思い出があります。
渋味の正体はタンニン!
焼酎でなぜ柿の渋抜きができるのでしょう。
じつは渋味の正体は汁に溶け出してるタンニンで、焼酎にはそれを不溶化させる力があるのだそうです。
舌がタンニンを感じなくなるので甘いのですね。
八百屋さんから買ってきた大きな渋柿ふたつ
さて11月中旬、つれあいが「見て見て!」と大ぶりな柿をふたつ、目の前に差しだしました。
「きれいでしょ」
見事な色・形に思わず買ってしまったそうです。
しかし2個入りパックのシールを家で確認すると、そこには「渋柿」と表示されていました。喜びが半減してしまったわけですが、何事もドンマイなつれあい、リビングの飾りにするそうです。
そこで思い出したのが、祖父のあの流儀です。インテリア小物の使命を終えた渋柿を焼酎で渋抜きしてみることにしたのです。

19日間で渋柿を甘柿に!
結論を先に申し上げると、僕の方法では丸19日間を要しました。一方柿のヘタの部分に焼酎を十分染み込ませ、温かい部屋に寝かせておけば1週間でできるそうです。
しかしその方法を知ったのは後のこと。検証できないので、ここはあくまで実際に僕が確かめた方法をご紹介します。
用紙するもの
甲類焼酎 25度
芋焼酎や麦焼酎などの乙類焼酎でもできるのでしょうが、さすがに匂い移りが心配なので、無臭の甲類焼酎がよいかと思います。
保存用ポリ袋 L(横30cm×縦40cm)
渋抜きする柿の量・サイズによります。今回は大ぶりな柿2個だったので、キッチンにストックしてあったこのサイズのポリ袋を使用しました。
渋抜きの手順
[st-step step_no=”1″][/st-step]

柿2個(580g)に対してお玉半杯(25cc)ほどの甲類焼酎をふりかけ、ポリ袋の口を結びます。
ポリ袋の破れるのが怖くてバットに載せ、1階の部屋の机の影となる床に置きました。
※繰り返しますが、温かいところのほうが早く渋抜きができるそうです。僕は未検証!
[st-step step_no=”2″][/st-step]

およそ2週間後の状態がこれ。左の柿が赤みを増してきました。

焼酎にも柿の色がうっすらついています。

念のため竹串を差し、舐めてみました。しっ、渋い! まだ早かった!
焼酎が足りないと思い、お玉半杯(25cc)ほど追加しました。
[st-step step_no=”3″][/st-step]

焼酎に漬け始めてから19日目。もう大丈夫だろう、ということで袋から取り出してみました。ふたつの柿がしっかり赤く熟した色になりました。
再度竹串を差し舐めてみると、もう渋くありません。

試しに包丁で切ってみると、この熟し具合。これなら美味しいに違いありません。

別の記事 でご紹介のとおり、スプーンですくい恐る恐る食べてみます。
いや、これは甘い。最高のデザートになっています。
焼酎のアルコールが残っているかと思いましたが、それも心配ないようです。そういえば子どもの頃、母親が反対するなか、祖父は平気で食べさせていましたし、僕も酔っぱらった記憶はありません。
時間は要しましたが、大成功の渋抜きでした。
今年はもう渋柿が手に入らないので作れませんが、来年は実家の庭の隅に1本だけ残っている渋柿で再挑戦したいと思います。
硬めの甘柿より、よほど美味しいのでこれをやらない手はありません。
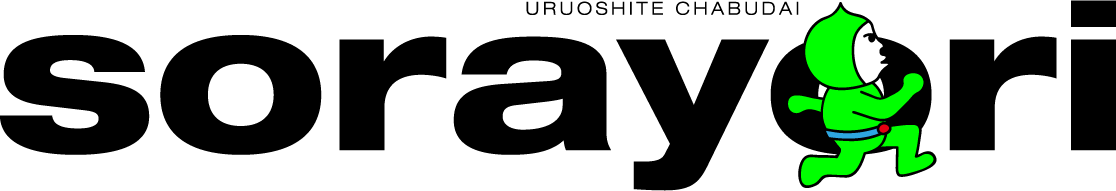


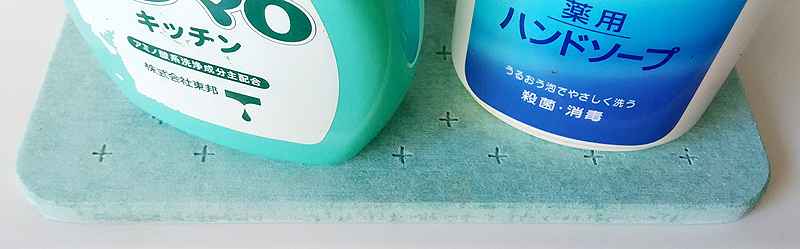
コメント